救命救急センター
救命救急センターについて
役割

県内に4施設ある救命救急センターのうち、東近江医療圏唯一の救命救急センターとして、地域の救急医療と重症患者さんの治療を担っています。
初期対応は、当科の専従医師と救急診療担当医師(レジデントを含む)が行い、いかなる疾患・外傷でもスピーディに対応できるよう、つねに各診療科のバックアップ体制を取っているのが強みです。
また、夜間・休日の時間帯の救急患者さんにも可能な限り対応できる体制となっています。特に緊急性の高い治療を要する患者さんについては、治療に関わる多職種のスタッフが合議し、多方面から検討した最新で高度な集学的治療を行っていきます。
初期対応は、当科の専従医師と救急診療担当医師(レジデントを含む)が行い、いかなる疾患・外傷でもスピーディに対応できるよう、つねに各診療科のバックアップ体制を取っているのが強みです。
また、夜間・休日の時間帯の救急患者さんにも可能な限り対応できる体制となっています。特に緊急性の高い治療を要する患者さんについては、治療に関わる多職種のスタッフが合議し、多方面から検討した最新で高度な集学的治療を行っていきます。



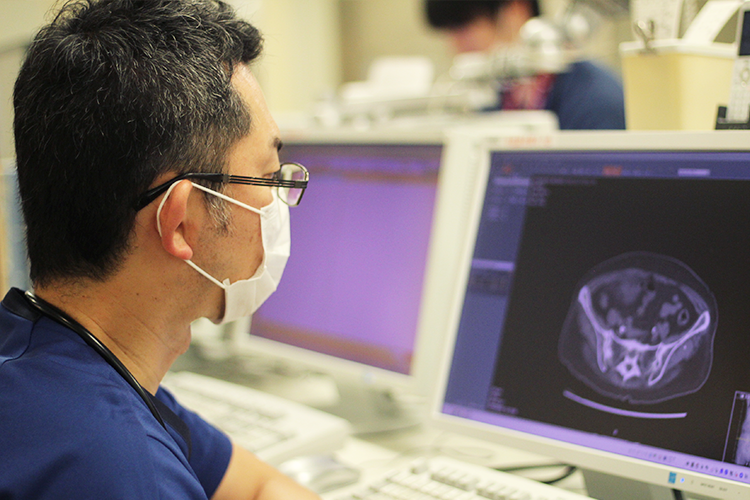
連携体制
担当する診療科
全診療科
体制
①救急車の搬送依頼をはじめ「No refusal polisy(依頼されたら断らない)」をコンセプトにした救急医療を目指しています。
②救急外来は一次から三次症例まで幅広く受け入れを行い、平日の時間内は専従医師(レジデントを含む)が初期対応を行い、その後、該当する診療科へ引き継ぎ、専門的な精査・加療を進めていくシステム(北米型ER)です。
③各診療科へのコンサルト、引き継ぎはオンコール体制となっています。
④夜間・休日などの時間外は外科系と内科系の救急診療担当医師が対応し、小児科、産婦人科は独立したダイレクトコールでの対応となっています。
⑤集中治療管理は、平日の時間内は専従医師、夜間などの時間外は専従医師と固定メンバー医が、主治医と協議を行いながら、多職種と連携して管理を行っています。
⑥センター内に、救急外来、救急病棟、集中治療室(ICU)を設置しています。
⑦当院は「日本救急医学会 救急科専門医指定施設」「災害拠点病院・DMAT(災害派遣医療チーム)の編成病院」です。
②救急外来は一次から三次症例まで幅広く受け入れを行い、平日の時間内は専従医師(レジデントを含む)が初期対応を行い、その後、該当する診療科へ引き継ぎ、専門的な精査・加療を進めていくシステム(北米型ER)です。
③各診療科へのコンサルト、引き継ぎはオンコール体制となっています。
④夜間・休日などの時間外は外科系と内科系の救急診療担当医師が対応し、小児科、産婦人科は独立したダイレクトコールでの対応となっています。
⑤集中治療管理は、平日の時間内は専従医師、夜間などの時間外は専従医師と固定メンバー医が、主治医と協議を行いながら、多職種と連携して管理を行っています。
⑥センター内に、救急外来、救急病棟、集中治療室(ICU)を設置しています。
⑦当院は「日本救急医学会 救急科専門医指定施設」「災害拠点病院・DMAT(災害派遣医療チーム)の編成病院」です。
救急外来からのお願い・注意点
- 重症度・緊急度の程度によって診察の順番が変わったり、長時間お待たせする場合がございます。
- 一旦近隣の医療機関を受診していただき、必要に応じて受診された医療機関からのご紹介をお願いする場合がございます。
- かかりつけの病気や緊急を要しない検査は対応できない場合がございます。
- 救急外来での投薬は、原則として1日分のみの処方としています。なくなってしまったお薬の処方などは行っていません。
- 専門性の高い診療科(眼科や耳鼻咽喉科など)はオンコールの医師を呼び出すため、医師の到着までお待ちいただくか、他院へ紹介する場合がございます。
以上、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
医師紹介
患者さんへのメッセージ
今後も“No refusal polisy”を掲げ、地域の救急医療に貢献していきます
東近江医療圏で発生した全救急患者の50~55%を当センターが対応し、特に圏内の重症度や緊急度の高い患者さん、他院で受け入れることができなかった患者さんを積極的に受け入れることができました。
医療圏唯一の三次救命救急センターとしての役割を十分担うことができたと自負しております。
今後も“No refusal polisy”を掲げ、地域の救急医療に多大なる貢献をしていきますので、引き続き、センター運営へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
医療圏唯一の三次救命救急センターとしての役割を十分担うことができたと自負しております。
今後も“No refusal polisy”を掲げ、地域の救急医療に多大なる貢献をしていきますので、引き続き、センター運営へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
